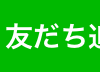猪肉を使った鍋が「牡丹鍋」と呼ばれているのは皆さんも知ってますよね。
実は他の肉にもこのように他の名前が付けられているのはご存知でしょうか⁈
猪(イノシシ)→牡丹(ぼたん)・山鯨(やまくじら)
鹿(シカ)→紅葉(もみじ)
馬(ウマ)→桜(さくら)
肉なのにどうしてこのように別の名前で呼ばれるのでしょうか?
今回はそんな疑問を解決していきたいと思います!
目次
肉を別の名前で呼ぶ理由は…隠語だった?!
さかのぼること江戸時代。
表向きには獣肉食はタブーとされていたそうです。
「禁じられていた」というよりは宗教的な意識の下で四つ脚の動物を食べることを良しとしなかった。ということのようです。
そんななか、当時「ももんじ屋(百獣屋)」と呼ばれる獣肉店が、肉を食べることを「薬喰い(くすりぐい)」と称し滋養をつけるという名目で肉料理を提供したり販売したりしていたそうです。
そこで、初めに書いたように隠語を使った訳ですね。
猪→牡丹・山鯨
鹿→紅葉
馬→桜
隠語(いんご)とは
ある特定の専門家や仲間内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のこと。 外部に秘密がもれないようにしたり、仲間意識を高めたりするために使われる。Wikipediaより
語源は?
それぞれの語源に関しては諸説あるようです。
今となっては真相のほどはわかりませんかいくつか紹介したいと思います。
猪→牡丹(ぼたん)・山鯨(やまくじら)
・盛り付けの際に薄切りにした肉を並べると牡丹の花に似ている
・古くからの『獅子に牡丹』『牡丹に唐獅子』という言葉から(意味:取り合わせの良いものの例え)
猪は他にも山鯨(やまくじら)という呼び方もあります。
猪はダメだけど「山の鯨」ならOKでしょ⁈というわけですね。
鹿→紅葉(もみじ)
・百人一首の中の「奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋はかなしき」という歌から
・花札の絵柄の「鹿に紅葉」という札から
上の2つの説は繋がっている?!

馬→桜(さくら)
・馬肉は桜の季節がおいしい説
・捌いた直後の新鮮な馬肉の色が桜色だから
・千葉県の佐倉にあった江戸幕府の牧場には優れた馬がそろっていたことから「馬=佐倉→桜」となった
番外編 兎(ウサギ)の数え方はどうして「羽」なのか?
兎(ウサギ)はどうして匹(ぴき)ではなく、羽(わ)なのか⁈
これもうさぎを鳥類として扱うことにして食べていた。ということのようです。
ピョンピョン跳ぶからですかね?!無理やりですねぇ~。
まとめ
当時は大っぴらに肉を食べることは出来なくても「薬」と称し、名前まで変えてひそかに食べていたわけです。
やっぱりおいしいからですよね~。
今となっては野生の鳥獣肉は「ジビエ」などと呼ばれてちょっとしたブームですし、肉を食べる食べないも自由に選べるし、ありがたいことです。
というわけで、今日もお肉をいただきます!
ではでは~

旅する美容室は 予約制 です
接客中は電話対応ができない事もありますので
ご予約 お問い合わせ 質問などは『LINE、各種SNS、メール』が助かります!
手が空き次第返信させていただきます!
どんなことでも気軽にお問い合わせくださいね♪